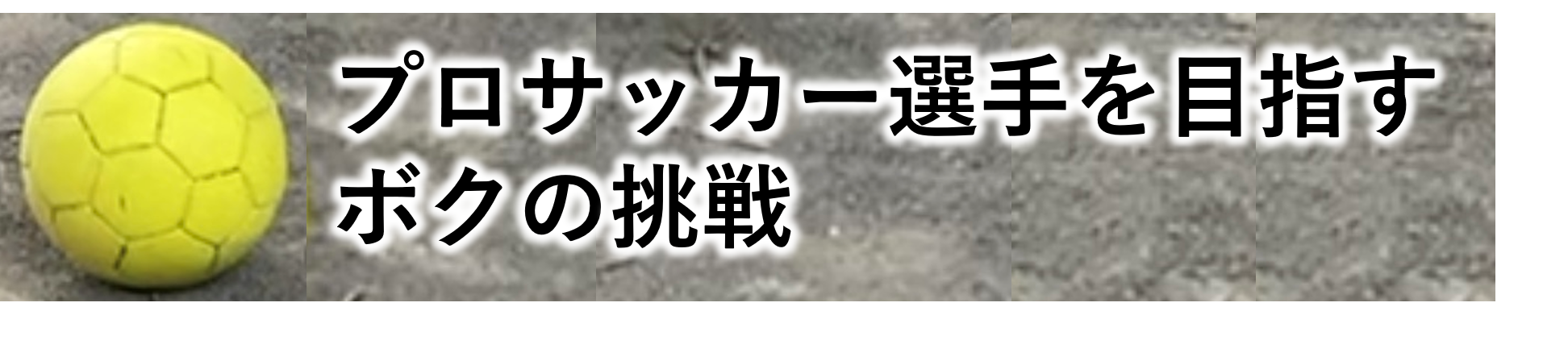プロのサッカー選手になるために最も近い道としてはジュニアユース(中学生年代)でJリーグの下部組織アカデミー(J下部)に入る事であり、そのためにも小学生年代ではJ下部ジュニアユースに入りやすいチームを選ぶということは重要なポイントの一つとなります。このことは「プロを意識した小学生年代のサッカーチームの選び方」という記事で書かせて頂きましたので先に見た上で本記事を読んで頂ければと思います。
-

-
プロを意識した小学生年代のサッカーチームの選び方
子どもがプロサッカー選手を目指す場合、数多くある少年サッカーチームから小学生年代を過ごすチームをどのように選ぶと最も効果的なのかということについてまとめたいと思います。 プロサッカー選手を目指す小学生 ...
続きを見る
本記事では息子が現在活動している神奈川県について具体的に少年サッカーのチームをリストアップしてみたいと思います。
J下部ジュニアユースに入りやすいチームのリストアップ方法について
具体的にチームをリストアップしてみますが、「プロを意識した小学生年代のサッカーチームの選び方」では、
- 毎年のように結果を出している強豪チーム
- J下部のジュニアユースに入った選手が多いチーム
- J下部ジュニアと試合をする機会が多いチーム
- 県や市のサッカー協会のWebサイトにて過去の公式戦の結果を確認する
- JリーグクラブのWebサイトにてJ下部ジュニアユースの選手の出身チームを確認する
としましたので、今回神奈川県編を例に具体的にしていきたいと思います。
step
1県の公式戦の成績からチームをレベル分け
まず、公式戦の結果という点についてですが、ここでは横浜や川崎というような市ではなく県の公式戦の結果をベースに考えていきたいと思います。そのため、神奈川県サッカー協会のホームページ「https://kanagawa-fa.gr.jp/」より対象となる公式戦をリストアップします。
神奈川県の主な公式戦
- 全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会
- 神奈川県チャンピオンシップU-12
- 日産CUP争奪 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 高学年の部
ここではこれら3大会を対象として下記の通りのレベル分けとしたいと思います。
チーム成績レベル
◎:直近5ヵ年分の対象大会(3大会)計15大会のうちベスト8以上の合計回数が10回以上(3回に2回以上)
○:直近5ヵ年分の対象大会(3大会)計15大会のうちベスト8以上の合計回数が8回以上(2回に1回以上)
△:直近5ヵ年分の対象大会(3大会)計15大会のうちベスト8以上の合計回数が5回以上(3回に1回以上)
×:それ以外
直近5か年分には対象年は含めないものとします。(例えば2023年の場合には2023年の結果は含めず2022年以前の5か年とします。)
つまり、
- 全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 → 2018年~2022年
- 神奈川県チャンピオンシップU-12 → 2017年~2022年 ※2020年は新型コロナの影響で開催なし
- 日産CUP争奪 神奈川県少年少女サッカー選手権大会 高学年の部 → 2017年~2022年 ※2020年は新型コロナの影響で開催なし
が対象となります。
5ヵ年に渡り安定して県大会でベスト8以上に勝ち上がれるチームというのは、普段からJ下部のスカウトが見る機会は多くなるため、セレクションのような1発勝負ではなくしっかりと見てもらえるのでJ下部アカデミークラスおよびその後の進路としてもJ下部ジュニアユースに行きやすいという傾向があります。その意味では、毎年のように結果を出しているという点で、チーム成績レベルが◎、○のチーム(もしくは範囲を広げるならば△を加えて)を選ぶということが一つの近道ということになります。もちろん、過去5ヵ年分を見ているので、設立されて間もないチームや最近急激に力をつけてきたというチームは含まれないことになりますが、今後何年か後に同様の方法で集計した場合に出てくるはずです。
step
2チーム成績に加えJ下部ジュニアユースの入団人数も加味してチームをレベル分け
次にJ下部ジュニアユースへの入団人数という点ですが、ここでは下記のようなルールでチームのリストアップしたいと思います。
- J下部ジュニアユースは当該年のシーズンでJ1、J2に在籍しているクラブの中でその県に本拠地を置くチームとする
- J下部ジュニアユースのチームはJリーグクラブのWebサイト上でジュニアユースとして記載があるもの
- Webサイト上の選手プロフィールよりジュニア年代の所属チームを確認する
つまり、2023年の神奈川県という意味ですと、下記のチームに入団した人数をカウントするということにしたいと思います。
対象のJ下部ジュニアユース
- 横浜Fマリノスジュニアユース
- 横浜Fマリノスジュニアユース追浜
- 川崎フロンターレU-15生田
- 川崎フロンターレU-15等々力
- 横浜FCジュニアユース
- 横浜FC鶴見ジュニアユース
- 湘南ベルマーレジュニアユース
- 湘南ベルマーレジュニアユースEAST
- 湘南ベルマーレジュニアユースWEST
注記
横浜FCは、2023年度より横浜FC戸塚ジュニアユースが廃止となり、横浜FCとは運営が別であるものの横浜FC鶴見が横浜FCのジュニアユース扱いになったため、2023年以降の横浜FC鶴見を計上します。また、神奈川県から例えば東京など他県のJ下部ジュニアユース(例えばFC東京や東京V、等)に行っているケースも一定数いるはずですがそれは考慮せず除外します。
これらのチームへの入団数を元に下記の基準でレベル分けをして、J下部ジュニアユースに入団しやすいチームをレベリングしたいと思います。公式戦の成績同様に5年分を対象にしたいと思いますが、調査した段階でWebサイトで確認できる範囲+過去に調査して結果が分かっている範囲とします。今回は初回ですので2021年、2022年、2023年の3年間分を対象年とします。(2020年以前の情報は現時点でWebサイト上で分からないため)
J下部ジュニアユース入団レベル
J下部:J下部ジュニアチーム
S:毎年4名(レギュラーの半数)以上がJ下部へ行くチーム、かつ、チーム成績◎
A+:毎年4名(レギュラーの半数)以上、もしくは、「毎年複数名がJ下部へ行くチーム、かつ、チーム成績◎、○」
A:毎年複数名、もしくは、「毎年1名はJ下部へ行くチーム、かつ、チーム成績◎、○、△」
B+:毎年1名以上、もしくは、ほぼ毎年複数名がJ下部へ行くチーム
B:ほぼ毎年1名はJ下部へ行くチーム、かつ、対象年数のJ下部入団人数合計が対象年数以上の水準
C:複数年でJ下部へ行くチーム
D:1年間だけJ下部へ行くチーム
注記
レベルBの「ほぼ毎年」とは対象年のおよそ80%の年とします。(およそとは小数点以下を四捨五入するためこのような表記にしています。例えば、対象年が3年であれば80%で2.4年ですが小数点以下を四捨五入して2年となり2年以上でほぼ毎年という意味となります。)また、対象年数の入団人数合計が対象年数以上というのは例えば、対象年数が3年であれば3年間のJ下部入団人数が3名以上という意味になります。
また、J下部のジュニアチームからジュニアユースへ上がる人が多くなるのは当然のことですのでJ下部チームは一旦除外する意味でも他とは分けたいと思います。J下部以外のチームは毎年どの程度の人数がJ下部ジュニアユースに行っているかというものをベースにしつつ、そこにチーム成績が良いとJ下部のスカウトに見てもらえる可能性が高いということを勘案してレベリングします。そのチームのレギュラークラスになれればJ下部に入れるのか、エース級なら入れるのか、チームとの関連はあまりなくあくまでも個の力によってJ下部ジュニアユースに入っているのか、というような傾向が見えてくるはずです。
ただし、このレベル分けですと、公式戦の結果からチームをリストアップした際と同様にチーム設立後間もないためにリストアップされないという可能性が出てきますので、念のために、対象年(今回の場合だと2021年、2022年、2023年)の合計入団人数Top10と、対象年の最新の年(今回の場合だと2023年)のJ下部入団人数Top10も併せてリストアップしておこうと思います。こちらにのみリストアップされる場合には比較的新しいチームであるが将来的には毎年のようにJ下部入団者数を多く輩出するようなJ下部ジュニアユースに入りやすいチームという可能性がありますので、Top10に入るようなチームは上記のチームレベルとは別にJ下部ジュニアユースに入りやすいチームと位置付けても良いかもしれません。なおこちらはJ下部ジュニアチームも含めたリストアップにしたいと思います。
J下部ジュニアユースに入りやすいチームのリストアップ結果
上記のリストアップ方法に基づきリストアップした結果を下記にまとめたいと思います。
step
1県の公式戦の成績からチームをレベル分け
神奈川県の公式戦の結果については神奈川県サッカー協会のホームページ「https://kanagawa-fa.gr.jp/」に全て掲載されていますので集計した結果を下記にまとめます。
チーム成績レベルの集計結果:◎、○、△合計10チーム
| レベル | チーム数 | チーム名(ベスト8以上の合計回数/15回) |
| ◎ | 2 | 川崎フロンターレU-12(11/15)、バディーSC(11/15) |
| ○ | 1 | SCH.FC(8/15) |
| △ | 7 | あざみ野FC(7/15)、横浜Fマリノスプライマリー(7/15)、JFC FUTURO(7/15)、大豆戸FC(7/15)、SF AT ISEHARA SC(6/15)、FCパーシモン(6/15)、足柄FC(5/15) |
step
2チーム成績に加えJ下部ジュニアユースの入団人数も加味してチームをレベル分け
JリーグクラブのWebサイトにはJ下部アカデミーのページがあり、そこにはジュニアユースに入団した選手のジュニア時代の所属チームが載っていますので集計した結果を下記にまとめます。
J下部ジュニアユース入団レベル:対象年2021年〜2023年の3年間の入団実績による全レベル合計123チーム(367人 2021年:110人、2022年:115人、2023年:142人)
| レベル | チーム数 | 人数 | 人数割合 | チーム名(対象年数のJ下部入団合計人数) |
| J下部 | 3 | 66人 | 18% | 川崎フロンターレU-12(28)、横浜Fマリノスプライマリー(24)、横浜Fマリノスプライマリー追浜(14) |
| S | 1 | 17人 | 4.6% | バディーSC(17) |
| A+ | 4 | 63人 | 17.2% | SCH.FC(23)、あざみ野FC(14)、JFC FUTURO(14)、TDFC(12) |
| A | 3 | 27人 | 7.4% | FCパーシモン(10)、中野島FC(9)、足柄FC(8) |
| B+ | 9 | 42人 | 11.4% | SF AT ISEHARA SC(6)、横浜すみれSC(6)、原FC(5)、横浜深園SC(5)、大豆戸FC(4)、FC本郷(4)、横浜港北SC(4)、海老名FC(4)、FC C.E.L(4) |
| B | 9 | 27人 | 7.4% | バディーSC中和田(3)、藤沢FC(3)、荻野FC(3)、登戸SC(3)、FC MAT(3)、六浦毎日SS(3)、FC鷹(3)、藤の木SC(3)、磯子SC(3) |
| C | 10 | 20人 | 5.4% | ※チーム名の記載は省略(全て下線なし) |
| D | 84 | 105人 | 28.6% | ※チーム名の記載は省略(全て下線なし) |
注記
上表内のチーム名に「下線あり」はチーム成績レベルが◎、○、△のチーム、「下線なし」はチーム成績レベルが◎、○、△ではないチームとなります。つまり、「下線なし」チームはチーム成績と比べ多くのJ下部ジュニアユース入団者を輩出しているということになります。(J下部である横浜Fマリノスプライマリー追浜も「下線なし」というのは意外な気がしました。)
対象年のJ下部合計入団者数Top10:対象年2021年〜2023年の3年間の合計入団者数の多いチームTop10
| 順位 | チーム名(対象年数のJ下部入団合計人数) |
| 1 | 川崎フロンターレU-12(28) |
| 2 | 横浜Fマリノスプライマリー(24) |
| 3 | SCH.FC(23) |
| 4 | バディーSC(17) |
| 5 | 横浜Fマリノスプライマリー追浜(14)、あざみ野FC(14)、JFC FUTURO(14) |
| 8 | TDFC(12) |
| 9 | FCパーシモン(10) |
| 10 | 中野島FC(9) |
最新年のJ下部入団者数Top10:対象年2021年〜2023年の最新年2023年の入団者数の多いチームTop10
| 順位 | チーム名(最新年のJ下部入団人数) |
| 1 | 川崎フロンターレU-12(9) |
| 2 | 横浜Fマリノスプライマリー(8)、SCH.FC(8) |
| 4 | JFC FUTURO(6)、足柄FC(6) |
| 6 | 横浜Fマリノスプライマリー追浜(5)、中野島FC(5)、SF AT ISEHARA SC(5) |
| 9 | バディーSC(4)、あざみ野FC(4) |
これら2つのTop10を見ると、今回は両方とも上記の「J下部ジュニアユース入団レベル」のB+以上のチームしかないことが分かります。
リストアップした結果から考えられること
J下部ジュニアユースに入りやすいチームという観点でリストアップして見ましたが、J下部ジュニアユース入団レベルがJ下部、S、A+、A(およびB+の一部)については毎年J下部ジュニアユースに入団しているということから、レベルA以上のチームであればJ下部ジュニアユースに入りやすいチームと言えると思います。(もちろんSやA+だとレギュラーの半数以上が毎年J下部ジュニアユースに行くレベルであるためよりJ下部ジュニアユースに入りやすいチームと言えます。)実際に、チームの成績レベルが上位のチームがこのレベルに並んでいます。レベルA以上のチームは今回の集計ではJ下部のジュニアチームを除くと8チームとなりますが、上表「J下部ジュニアユース入団レベル」の人数割合が示す通り、これら8チームでJ下部入団人数の約30%を占めています。J下部ジュニアチームからジュニアユースへの入団(ほぼ昇格)が全体の約18%を占めていますので合わせると約48%、つまりほぼ半数となります。さらに少しだけ範囲を広げてレベルBも含めてみると、B+とBの計18チームを合わせると約18.8%となり、J下部、S、A+、A、B+、Bで約66%と全体の2/3を占める結果となりましたので、このあたりのチームでジュニア年代を過ごすことがJ下部ジュニアユースへの近道であると考えられます。(レベルA以上のチームはJ下部ジュニアチームを含めて11チームしかありませんのでこれらのチームに入ることもレギュラーを取ることもなかなか大変だと思うわけですが、レベルB(B+、B)も含めると29チームに増えますので、より現実的なねらい目になるのでは思います。)
興味深いのは、J下部のジュニアチームといえどもジュニアユースに昇格できない選手が一定数いるようで、チーム内の選手数も違うもののレベルSやA+のチームの中にはJ下部のジュニアチームよりも多くの人数がJ下部ジュニアユースに行くチームもありますので、J下部ジュニアチームが最もジュニアユースへ行きやすいとも言えないという点です。これは、J下部のジュニアチームに所属するということは、チーム内での競争相手のレベルが非常に高いため試合に出る機会が減ってしまうということもありますし、そのクラブのジュニアユースに昇格するということになり、他のクラブのJ下部に行くことは基本的にはありませんので、J下部ジュニアチームに入るイコール選択肢が狭まるとも言えるわけです。
一方、レベルC、Dの合計は94チームとなり、そこから残り1/3(約34%程度)がJ下部ジュニアユースへ入団していますので、結局はどのチームにいてもJ下部ジュニアユースに入るチャンスはあるということも分かります。このことから、J下部ジュニアユースに入るためにはチームの影響より、その選手個人の力によるところが大きく、つまりは実力や将来性次第で誰にでもJ下部ジュニアユースに入れる可能性があるということが言えると思います。
まとめ
・J下部ジュニアチームを含むレベルB以上のチーム(29チーム)はJ下部ジュニアユースに入る人数が多い(全体の約2/3の人数)(強い個が集まりやすく強い個に育ちやすい+J下部から見られる機会が多い環境)
・レベルC、Dのチーム(94チーム)でも個の実力や将来性が認められればJ下部ジュニアユースに入れる(全体の約1/3の人数)(チームによらず強い個になれる)
この記事は以上となりますが、参考になれば嬉しく思います。