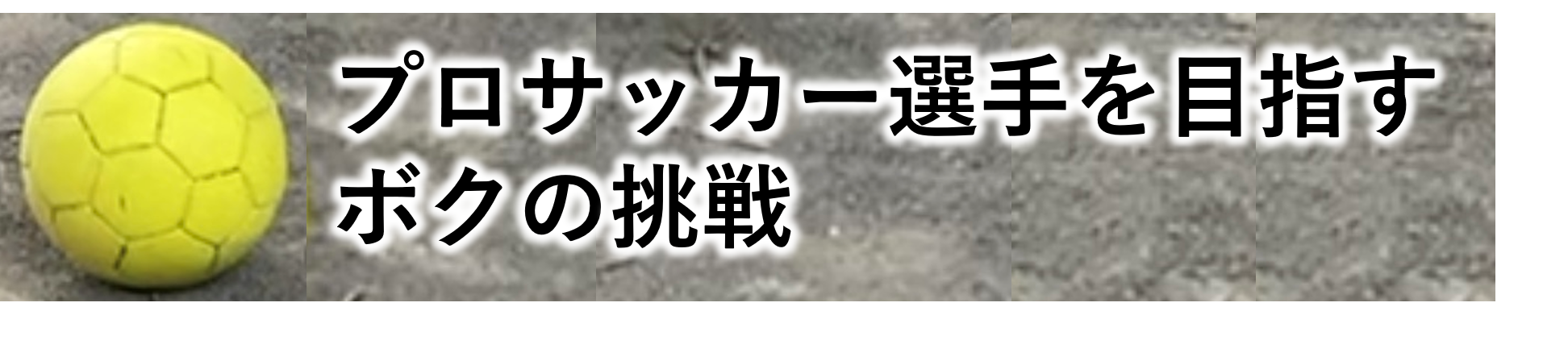息子のJ下部組織(J下部)のセレクションを受けた経験を元にして共通点やクラブごとの違いをまとめます。J下部を目指す場合の参考になれば幸いです。
J下部組織のジュニア年代のチーム、スクールの構成について
まず、大きくアカデミーとスクールという2つに分かれます。
- アカデミー → 将来そのクラブのトップチームで活躍する選手を育成するための組織です。Jリーグ下部組織(J下部)はこちらになります。
- スクール → Jリーグのクラブが運営しているもののそのクラブの選手を育成する目的ではなく、サッカーやクラブの普及活動という位置付けです。こちらはJ下部ではありません。
この違いがとても重要で、プロサッカー選手を目指す子どもたちはアカデミーを目指すわけです。もちろん、最初はスクールの方に通いつつ、そこからステップアップする形でアカデミーへ入るということもありますし、クラブによってはアカデミーとスクールを一体として運営しておりその境がわかりにくい場合もあるのですが、基本的にはアカデミーとスクールは全くの別物ということを理解しておく必要があります。
アカデミーとスクールはさらに細分化されます。
アカデミー
-
チーム
→ 所属選手は選手登録されチームとして活動しています。いわゆるアカデミーといえばチームのことを指すためジュニア年代においてもこのチームがアカデミーのメインとなります。ただし、Jクラブによってはチームを持たないところも一定数あります。
-
クラス
→ こちらは逆に選手登録はせずに他で自分のチームに所属している子どもたちが、そのクラブのトップチームを目指すためにジュニアユース年代でチーム(U-13とかU-15)に所属するために、週1、2回程度集まり練習をするアカデミー内のスクールのような位置付けです。選手の囲い込みという重要な目的もあります。どのクラブもセレクションに合格する必要があるかスカウトされる必要があるという点とジュニアユース年代に向けて指導しつつその過程で選手を選別するということは共通しており、スクールとの大きな違いとなります。また、クラブによる違いで大きなものとして、アカデミーとして明確にスクールとは別の組織という位置付けのクラブなのか、スクールの特別クラスというような位置付けのクラブなのかという点になります。ここではアカデミーとしてのクラスがないクラブについては、目的がアカデミーとしてのものであれば厳密にはアカデミーではなくスクールの特別クラスもアカデミー相当として扱いたいと思います。つまり、アカデミーのクラスは下記の2パターンに分かれるということになります。
- アカデミー所属クラス → アカデミーの一員であり、クラブのWebサイトにも名前や顔写真が載ります。また、アカデミーの一員のため、他のJクラブのアカデミークラスとの掛け持ちは不可(スクール特別クラス含め不可)となります。人数も少人数であることが多く、その分、そのクラブへのジュニアユースへの昇格可能性が高いと言えます。
- スクール特別クラス → スクールではありますがアカデミー相当となります。練習もアカデミーのコーチが担当することになります。アカデミーではないためクラブのWebサイトに名前は載りません。そのため、基本的には他のJクラブのスクール特別クラスとの掛け持ちも可能となります。ただし、アカデミーではないこともあり人数はある程度多めであるためジュニアユースへの昇格可能性はアカデミー所属と比べて低い傾向にあります。
スクール
-
選抜クラス
→ スクールの中でも希望しただけで無条件に入会できるものではなく、コーチからの推薦やセレクション合格により入れるというタイプのスクールです。ですので、ある一定のレベルの子達が集まりますので、よりサッカー上達に適した環境と言えるでしょう。プロを目指すもののアカデミーには入れないレベルの場合にはまずスクールの選抜クラスからレベルアップしてアカデミーを目指す子どもたちも多いです。
-
一般クラス
→ 選抜以外のスクールのことです。学年や年代ごとの場合もあれば、ドリブルやゲームというものに特化したようなものもありさまざまな形がありますが、希望すれば入会できる(定員に空きがあれば)ため、子どもたちのレベル差や目的は実にさまざまです。
神奈川県や東京都のJ1クラブの場合にはどうなるか?
2022年シーズン終了時点(2023シーズンの開始時点)の神奈川県と東京都のJ1クラブについて、上記で整理したもので当てはめてみると下の表のようになります。なお、スクールの一般クラスは記載を省略します。
| クラブ名 | アカデミー ※J下部として扱う | スクール | ||
| チーム | アカデミー所属クラス | スクール特別クラス | 選抜クラス | |
| 川崎フロンターレ | U-10/U-12 | なし | エリートクラス | アバンテ |
| 横浜Fマリノス | プライマリー、プライマリー追浜 | なし | スペシャルクラス | 強化クラス |
| 横浜FC | なし | U-12強化カテゴリー | なし | アスリートコーススペシャル、アスリートコース |
| 湘南ベルマーレ | なし | 強化特待クラス | なし | スーパークラス、アドヴァンスクラス |
| FC東京 | なし | なし | アドバンスクラス | 選抜クラス |
クラブによってアカデミーの構成がかなり違うということが分かると思います。ポイントはジュニアチームがあるかどうか、アカデミークラスの構成としてアカデミー所属クラスがあるかないかという点となります。
これを見ると、
- ジュニアチームがある場合にはアカデミー所属クラスはない → 川崎フロンターレ、横浜Fマリノスのパターン
- ジュニアチームがなく、アカデミー所属クラスがある → 横浜FC、湘南ベルマーレのパターン
- ジュニアチームもアカデミー所属クラスもなく、アカデミー相当の特別クラスがある → FC東京のパターン
となっており、Jクラブを全て調べているわけではありませんが、おそらくはどのクラブもこのいずれかに当てはまるのではないか?と推測しています。
横浜FCのアスリートコーススペシャルと湘南ベルマーレのスーパークラスについてはアカデミークラスの特別クラスに近い位置付けとも考えられるのですが、両クラブともアカデミー所属クラスがあるためここではアカデミー扱いとしないこととします。
ちなみに、セレクションの仕方はクラブによって結構違います。例えば、川崎フロンターレはアカデミーのチーム(U-10)と特別クラス(エリートクラス)では別々にセレクションを行っていましたが、横浜Fマリノスは同時に行っていましたし、横浜FCはアカデミー所属クラス(U-12強化カテゴリー)とスクール選抜クラス(アスリートコース)を同時にセレクションをしていました。余談ですが、私は最初横浜FCにもジュニアのチームがあると勘違いし、それがU-12強化カテゴリーだと思いセレクションに申し込みましたが、U-12強化カテゴリーはアカデミーのチームではなくアカデミー所属クラスであり、さらに、アスリートコースも同時にセレクションを実施というのは実施要項で分かっていましたが、アスリートコースはスクールの選抜クラスの位置付けということすら知らずにセレクションに申し込んでいたというレベルでした笑
2023年に川崎フロンターレはU-10とU-12を区別せずまとめてU-12とするようになりました。また、U-12とエリートクラスのセレクションも同時に開催するようになり、横浜Fマリノスに近い実施方法になっています。
J下部のアカデミーやジュニアユースをどのように目指すか?
ジュニア年代のことだけを考えているわけではなく、あくまでもプロを目指すという場合においては、ジュニアユース年代でJリーグ下部組織に入ることを目指すことが多いと思います。そのためには、ジュニア年代でアカデミーのチームかクラスのどちらかに入りそこからジュニアユースに昇格することが一番の近道ですが、それ以外にもJ下部からスカウトされるかJ下部ジュニアユースのセレクションに合格し直接入る道もあります。まとめると下記のような形になると思います。
- アカデミーのチームに入る → チームのセレクションに合格、アカデミーのクラスから移る(スカウトされる場合は一度アカデミーのクラスに入ることが想定されます)
- アカデミーのクラスに入る → 自チームでのプレーを見てスカウトされる、アカデミークラスのセレクションに合格、スクールの選抜クラスから昇格
- ジュニアユースに昇格する(昇格できない場合もあり)
もしくは、
- ジュニアユースに直接入る → 自チームでのプレーを見てスカウトされる、ジュニアユースのセレクションに合格
Jリーグ下部組織により多少の差はあると思いますが、概ねこのパターンとなりますので、どのようにアプローチしていくかということを考えてみると良いと思います。もしジュニアユースを見据えてスクールを選ぶとしたら、スクールの選抜クラスにはまず入る必要がありますが、さらにそのスクールの選抜クラスでの評価が高い場合にはアカデミーのクラスへの昇格できるのかどうか、という点が非常に重要だと考えています。
ちなみに、息子の場合はジュニア年代のチームには所属したため、J下部のアカデミーのチームは選択肢から外れます。ですので、アカデミーのクラスに入りそこからジュニアユースに昇格することをまずは目指しつつ、チームでの活動を通してJ下部のアカデミーのクラスにスカウトされるということを視野に入れてやる形です。それが難しい場合には、J下部のジュニアユースに直接入る道を狙うという形になるわけですが、いずれにしても、プロを目指すという場合においては、チームやスクールでの日々の練習や試合が常にJ下部のジュニアユースへの道につながるという意識を持って取り組むことが重要だと考えています。